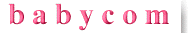『人間が生まれるということ』
●先住民族の智恵
初夏の北海道に行ってきた。札幌から日高を抜け、旭川から阿寒湖、釧路へと、ひとりでドライブを楽しんだ。各地で先輩の助産婦を訪ね、昔の話を聞いてまわる旅だ。北海道へ行くとまず、その空気の違いを感じる。「ここは日本じゃない」そう感じられるのだ。とにかく空が広い。なだらかな丘陵がどこまでも広がっていて、ポプラの並木が続く。そんな風景はときとして私には荒涼として感じられ、いつか行った中国のウィグル自治区を思い出させる。そこは日本古来の文化圏ではなく、大陸の空気が漂っているように思うのだ。
今回はそんな北海道に住む先住民、アイヌの聖地と呼ばれる場所の2ケ所でキャンプした。ひとつは日高地方の二風谷という村。そこにはかつてサケがあふれるように上ってきたという美しい沙流川があり、そのほとりでひとりキャンプをした。もうひとつは、阿寒湖の近くのオンネトーという湖。時間帯によって水の色が五色に変わると言われるその小さな湖は、深いコバルトブルーから淡い水色まで、本当に五色の変化を私は数えることができた。
そのそばに、湯の滝という、これもまたそれはそれは美しい滝がある。しかもそこには温泉が湧き出していて、ちゃあんと露天風呂もある。滝の脇を上っていくと、温泉の源泉の近くに、野性の鹿が2頭、薮の中から私を見ているのだった。
大地から水があふれ、湯の煙がたち上る。その光景は、大地そのものに力があるということを強く感じさせる。大地から湯が湧く。地球は生きている。そのことを実感させてくれるのだ。
この湯の滝に行ったのは、実はブラジルのインディオの絵描きであるアユトン・クレナックという人が来日した際に寄ったということを知ったからだった。それを私はビデオで見て、直観的に「行きたい」と思ったのだ。ブラジルという地球の裏側からやってきたインディオが、北海道のアイヌに会いに行く。考えてみれば先住民という共通項をもつ彼らにとって、それは自然な行為なのだけれど、それを聞いたとき私の中で「アイヌ」という言葉が久しぶりにコロコロと心地よい響きを放った。
私がアイヌに出会ったのは、6年前。二風谷に住む、「愛子ばば」と呼ばれる青木愛子さんという産婆に会いにいったことに始まる。彼女はシャーマンにして治療師、そして先祖代々受け継がれた産婆の家系に生まれた。愛子ばばはその2年後に亡くなったので、私は1度しか彼女にあったことはなかったけれど、不思議な力をもった人だった。今回の北海道行きでは、愛子ばばのお墓参りも大切なスケジュールのひとつだ。私は彼女や彼女の甥ごさんから、アイヌのもつプリミティブな精神性を教えてもらった。「木にも水にも川にも山にも精霊がいると、アイヌは信じているのです」と。そして愛子ばばは私の目の前で、なにやらお祈りみたいなしぐさをするのだった。
私はアユトン氏を映像の中で見て、強く引かれるものを感じた。正直に申し上げると、その男は実に私好みでかっこよかった。しかし一番驚いたのは、彼が祈りにも似た行為をしていたことだ。彼は滝の前にたたずみ、目を閉じてその場の気配を感じているように思えた。コメントには「彼は自分たちの友人である水の精霊に祈りをささげた」とあった。自然の中で祈りをささげる男。大きな古い木に手を当てて、さも愛しいとでもいうかのように木の幹を軽く何度も手で叩いていた。
「愛子ばばと同じだ」。私はそう感じた。「本物のインディオだ」。私はなんだかすごくうれしくなって、「北海道に行くなら、この湯の滝を訪れてみよう」と思ったのだった。
で、行ってみると、やはりその場所は大地がエネルギーを放っていた。都市ではもうとっくに感じられなくなった大地や地球の力だ。その自然は私をやさしく包んでくれた。アイヌも、ブラジルの先住民たちも、こうした大きな自然の中に身をおいて、自然に癒されていたのだろう。
大きな自然を感じ、大地や水とともに生きる生活は、都会の生活からは遠く離れてしまった。でも、今こうした先住民たちの智恵を私たちは必要としているのではないかと思う。自然を管理することによって、文明を築きあげ、自然を克服することに喜びを感じてきた文明人だけれど、その管理社会に自分があわなくなってしまっていると感じる人たちがいる。だから田舎暮らしの生活やガーデニングなどが脚光を浴びているのだ。でも、現実的には自然な生活を夢見ていても、仕事の都合を考えると都市生活はやめるにやめられない、そんな人が多いのかもしれない。一方で、あまりに自然とかけ離れてしまったがゆえに、そうした窮屈な思いすら感じなくなってしまっている人もいるように思う。都市は人間と自然との接点を遮断する機能を十分に備えているのだ。
でも、世の中には物やお金では得られないものもある。データにおきかえられない世界はやはり存在する。管理しきれない自然があり、その自然は多くのことを私たちに教えてくれる。それを感じられる人に、私はひかれる。
アユトン氏はインタビューの中で、「都会で生きていきやすい人間は、毎日同じことを繰り返し、それに対して疑問をいだかない人です。今、世界中の子どもたちが暴力的になっているのを大人たちは不安気に見ていますが、あれは子どもたちが管理社会に適応できなくなったその反動なのです」
東京生まれで東京育ちの私が、河口湖の田舎に家を借りて住みだしたのも、都会の管理社会に息苦しさを感じたからだ。都会は経済、科学優先の男性的な価値観に基づいている。のんびり、先を急がず、足元を見ている子どもにはその早さは必要のないものだと思う。都会のリズムは、大人だけでなく、子どもの感じる能力まで、奪いとってしまっているのではないだろうか。
|
 産院選びのためのお産情報_お産コラム
産院選びのためのお産情報_お産コラム
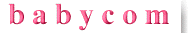
 産院選びのためのお産情報_お産コラム
産院選びのためのお産情報_お産コラム