子ども環境問題2
Interview 専門家インタビュー2環境ホルモンと妊婦、胎児の関係
インタビュー:森 千里 先生(千葉大学大学院教授)2004年11月掲載(プロフィールは掲載当時)
環境ホルモンについて研究している森千里先生は「環境ホルモンに対してもっとも悪影響が心配されるのは胎児」だと言います。先生の研究では、子宮のなかにいる赤ちゃんが環境ホルモンに汚染されていることがわかりました。そして最も懸念されるのが、環境ホルモンの『複合汚染』です。
「少量なら大丈夫」と言われて久しい環境ホルモンですが、その認識が今、本当かどうか疑われています。個々では微量な環境ホルモンも、ひとまとめにすれば身体に悪い影響があるのではないか?最近の研究では、そう考えられるデータが報告され始めています。
おなかの赤ちゃんへの影響は?
具体的にどういった対策をとればいいのか? 森先生に伺いました。
環境ホルモンと妊婦、胎児の関係
インタビュー:森 千里 先生(千葉大学大学院教授)
 「化学物質のなかには、ホルモンと似た作用やホルモンの働きを阻害する作用を持つものがあります。現在、環境省が『環境ホルモンと疑われる物質』としているものは65種類。これらの化学物質が人体に取り込まれると、身体の正常な発達や機能を妨げたりする可能性があるのです。それが環境ホルモンと呼ばれるもので『内分泌かく乱物質』とも言われます。
「化学物質のなかには、ホルモンと似た作用やホルモンの働きを阻害する作用を持つものがあります。現在、環境省が『環境ホルモンと疑われる物質』としているものは65種類。これらの化学物質が人体に取り込まれると、身体の正常な発達や機能を妨げたりする可能性があるのです。それが環境ホルモンと呼ばれるもので『内分泌かく乱物質』とも言われます。環境ホルモンがもたらす人体への影響はまだ不確定な点が多いのですが、関係が疑われるものとして、精子の数の減少、生殖器の異常・腫瘍、甲状腺機能障害、女性の思春期の早期化などがあげられています。アレルギー、アトピーなどの免疫系や神経系への影響も疑われています」
私たちにとっては子宮のなかにいる赤ちゃんへの影響が一番心配なのですが?
 「私は環境中にある化学物質の影響を一番受けるのは胎児であることに気付き、胎児に対する複合汚染の研究を始めました。私がこの研究を始める前は、単独の化学物質が胎児に及ぼす影響に関する研究はありましたが、複数の化学物質の影響に関する研究は世界的にありませんでした。
「私は環境中にある化学物質の影響を一番受けるのは胎児であることに気付き、胎児に対する複合汚染の研究を始めました。私がこの研究を始める前は、単独の化学物質が胎児に及ぼす影響に関する研究はありましたが、複数の化学物質の影響に関する研究は世界的にありませんでした。現在、化学物質の濃度規制の基準値は、一つ一つの化学物質についてのものです。しかし、現実には私たちがさらされている化学物質は一種類ではない。数十から数百種類もあるのです。はたして、個々の化学物質の基準値さえクリアーしていれば、人体に影響がないと言えるのでしょうか?
しかも、その規制値は成人を基準にしたものです。化学物質に対する感受性がより高い胎児に対して、はたして問題がないのかどうか、非常に疑問です。
実際に調べてみると、現代の胎児は例外なく環境汚染物質にさらされています。出産後のへその緒に含まれる化学物質を測定したところ、数十種類の化学物質が検出されました。また、他の研究室からは、羊水からも化学物質が検出されていることを報告しています」
それは妊婦さんたちにはかなりショックなことですね!
 「現時点で、環境ホルモンのヒト胎児への影響は、はっきりわかっていないのですが、これまでの歴史の中で胎盤を経由して化学物質が胎児に移行して起こった悲しい事例としては、1950年代の胎児性水俣病、1960年代に手足の形成不全が起こったサリドマイドの事例、そして、1970年代に切迫流産を防ぐために投与された合成女性ホルモン(DES)によって生まれた子どもが成人になって膣がんや精子数減少が起こったDESシンドロームという事例があります。また、最近では『胎児プログラミング』と言う概念が提唱され、胎児期などの発生の重要な時期に、母体栄養、ステロイドや化学物質曝露が、成人期の代謝や生理機能に影響を及ぼし、高血圧、糖尿病、肥満、精神疾患を引き起こすと言われるようなってきています。つまり、生まれた時は正常でも、成長してから胎児期の影響があらわれることがあるのです」
「現時点で、環境ホルモンのヒト胎児への影響は、はっきりわかっていないのですが、これまでの歴史の中で胎盤を経由して化学物質が胎児に移行して起こった悲しい事例としては、1950年代の胎児性水俣病、1960年代に手足の形成不全が起こったサリドマイドの事例、そして、1970年代に切迫流産を防ぐために投与された合成女性ホルモン(DES)によって生まれた子どもが成人になって膣がんや精子数減少が起こったDESシンドロームという事例があります。また、最近では『胎児プログラミング』と言う概念が提唱され、胎児期などの発生の重要な時期に、母体栄養、ステロイドや化学物質曝露が、成人期の代謝や生理機能に影響を及ぼし、高血圧、糖尿病、肥満、精神疾患を引き起こすと言われるようなってきています。つまり、生まれた時は正常でも、成長してから胎児期の影響があらわれることがあるのです」まるで時限爆弾のように影響が現れるかもしれない、ということですね。
 「その理由は3つ考えられます。まず一つは、胎児は大人と比べて身体が小さいという点。風邪薬を例にあげるとわかりやすいと思いますが、子どもは大人よりも飲む量が少ない。大人と同じ量を取り込んだ場合、子どもや胎児は身体に取り込む物質に対する影響が、大人と比べて大きいということがわかります。
「その理由は3つ考えられます。まず一つは、胎児は大人と比べて身体が小さいという点。風邪薬を例にあげるとわかりやすいと思いますが、子どもは大人よりも飲む量が少ない。大人と同じ量を取り込んだ場合、子どもや胎児は身体に取り込む物質に対する影響が、大人と比べて大きいということがわかります。二つ目は、胎児は化学物質が入ってきたときの代謝や排出機構が大人のようにまだ出来上がっていないことが挙げられます。
そして、もうひとつの理由としては、胎児は発生・発達の途中にあるので非常に変化が起こりやすいという点です。60年代に手足の形成不全を起こしたつわり防止薬、サリドマイドの場合、妊娠の初期に飲むと、赤ちゃんの手足に先天異常を引き起こします。しかしこの時期を過ぎてしまえば飲んでも影響はありません。現在では、サリドマイドはエイズによる難治性口内炎の効果的な治療薬としてアメリカで認可を受けています。このことから、細胞が分化して器官へと発達している時期は、化学物質による影響を受けやすいということがわかります。受精卵から胎児へと発達してゆくときには、様々な複雑な化学反応が起こっている。そこへ、身体をつくるプログラムを狂わせる環境ホルモンが加わると、生殖系、免疫系そして精神・神経の発達過程に悪い影響が出る可能性が高いと考えられます」
母親が飲んだものが直接、赤ちゃんにとどいてしまうのですか?
ある程度、胎盤でブロックされるのではないかと思うのですが。
 「確かに、胎盤は自然のなかにある毒物や病原菌などの有害なものから赤ちゃんを守るための関所のような役割をもっています。しかし、残念ながらウイルス、タバコのニコチン、アルコール、ある種の化学物質はこの関所を通り抜け、胎児に直接影響が現れることがあります」
「確かに、胎盤は自然のなかにある毒物や病原菌などの有害なものから赤ちゃんを守るための関所のような役割をもっています。しかし、残念ながらウイルス、タバコのニコチン、アルコール、ある種の化学物質はこの関所を通り抜け、胎児に直接影響が現れることがあります」
赤ちゃんを守ることを胎盤まかせにしてはいけないのですね。
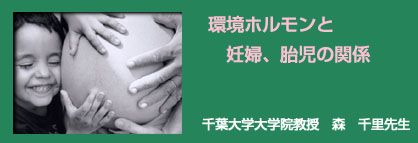
 「先ほども言いましたが、胎児の化学物質に対する感受性が最も高い妊娠初期の頃は特に注意が必要です。受精から第8週目まで、妊娠2〜3ヶ月までの頃を『ウインドウ期(高感受期)』と言います。細胞分裂が盛んで、ほとんどの臓器や器官がつくられる時期にあたります。この頃に胎児が環境ホルモンにさらされると、先天異常や健康障害が出やすいことが動物実験で報告されています」
「先ほども言いましたが、胎児の化学物質に対する感受性が最も高い妊娠初期の頃は特に注意が必要です。受精から第8週目まで、妊娠2〜3ヶ月までの頃を『ウインドウ期(高感受期)』と言います。細胞分裂が盛んで、ほとんどの臓器や器官がつくられる時期にあたります。この頃に胎児が環境ホルモンにさらされると、先天異常や健康障害が出やすいことが動物実験で報告されています」 妊娠2ヶ月といえば、妊娠に気づくか気づかないか、という頃ですよね
 「その通りです。妊娠、出産を考える女性ならば、この時期だけ気をつければいいというわけではありません。環境ホルモンには身体から代謝されやすい水溶性のものと、蓄積されやすい脂溶性のものがあります。妊娠したそのとき、すでにお母さんの身体に蓄積性の高い化学物質が残留していることもあります。妊娠がわかってから対策をとっても遅いということです。特に、第一子を生む年令が高くなるほど、蓄積される化学物質の量が多く、胎児への曝露が多くなる可能性が高い。将来、子どもをつくることを考える女性、男性は日頃から化学物質に暴露しない生活を考えることが重要なのです」
「その通りです。妊娠、出産を考える女性ならば、この時期だけ気をつければいいというわけではありません。環境ホルモンには身体から代謝されやすい水溶性のものと、蓄積されやすい脂溶性のものがあります。妊娠したそのとき、すでにお母さんの身体に蓄積性の高い化学物質が残留していることもあります。妊娠がわかってから対策をとっても遅いということです。特に、第一子を生む年令が高くなるほど、蓄積される化学物質の量が多く、胎児への曝露が多くなる可能性が高い。将来、子どもをつくることを考える女性、男性は日頃から化学物質に暴露しない生活を考えることが重要なのです」妊娠前からの対応策として、生活のなかで注意すべきことは?
 「主に食事に注意を向けることです。
「主に食事に注意を向けることです。環境ホルモンは食べ物や飲み物から、皮膚から、呼吸から身体に入ってきます。なかでも一番たくさんの化学物質を取り込むルートが飲食。農薬や薬、食物連鎖によって濃縮された環境化学物質などがあります。曝露のリスクを下げる方法のひとつとしては、片寄った食事をしないこと。ある種の食品を毎日食べていたとして、それが化学物質の曝露源だとしたら、当然、身体に入る化学物質の量は多くなることに。バランスよく、色々なものを食べることが大切です。
また、脂肪を多くとり過ぎないことも重要です。化学物質には先程お話したように水溶性と脂溶性のものがあります。水溶性のものは尿で体外に排出されやすいのですが、ダイオキシンなどの脂溶性の化学物質は脂肪に溶け込み、体内に蓄積されやすい。そのため、脂肪の多い食事はリスクが高いと言えます。
逆に、多く摂取したほうがいいと考えられているのが食物繊維。化学物質の排出を助けるという研究報告がありますので、リスク低減の可能性はあるでしょう」
食事以外に気をつけるべき点は?
 「衣食住のなかで使われる防虫剤、抗菌剤などの薬品は避けた方が無難でしょう。周りで虫が死んでいる環境に、人間がいてもまったく無害である、とは考えにくい。とくに長時間そういった環境にさらされないようにしたほうがいいと思います。他に曝露の機会が多いものとしてタバコがあります。本人が吸っていなくても、吸っている人の近くにいるだけで曝露しますから、妊婦や子どもはなるべくそういった環境は避けるようにすべきでしょう」
「衣食住のなかで使われる防虫剤、抗菌剤などの薬品は避けた方が無難でしょう。周りで虫が死んでいる環境に、人間がいてもまったく無害である、とは考えにくい。とくに長時間そういった環境にさらされないようにしたほうがいいと思います。他に曝露の機会が多いものとしてタバコがあります。本人が吸っていなくても、吸っている人の近くにいるだけで曝露しますから、妊婦や子どもはなるべくそういった環境は避けるようにすべきでしょう」個人レベルでできることはいろいろとあるのですね。
しかし、もし、すでに大量に体内に化学物質が蓄積されている場合はどうすればいいのでしょう?
 「自分の化学物質の蓄積量を知り、積極的に対策をとる方法があります。千葉大学では、今、その試みを行っています。体内の化学物質の血中濃度を測ってみて、低ければ安心してもらいます。多くの方は、不安が先に立っているケースが多いからです。そして、少し高いケースには、今後どのようなことに気をつければよいかのリスクコミュニケーションや環境教育を行い、生活習慣病におけるライフスタイルの改善を含めた予防的対応を推奨します。
「自分の化学物質の蓄積量を知り、積極的に対策をとる方法があります。千葉大学では、今、その試みを行っています。体内の化学物質の血中濃度を測ってみて、低ければ安心してもらいます。多くの方は、不安が先に立っているケースが多いからです。そして、少し高いケースには、今後どのようなことに気をつければよいかのリスクコミュニケーションや環境教育を行い、生活習慣病におけるライフスタイルの改善を含めた予防的対応を推奨します。そして、もし非常に高いケースであれば、これは非常にまれなケースと思っておりますが、その方にはその蓄積された化学物質を減らす医学的対応に進むようにアドバイスをしようと思っております。これまでのところ、内科学教室との試験的試みで、高コレステロール血症の治療薬を半年服用してもらって、血中のダイオキシン量が3割ほど軽減した例もあります。この試みの目指す所は、未来世代のための化学物質汚染対策です。
具体的には、妊娠前の方で化学物質の影響が気になる方に血中濃度測定を受けてもらい、どのように対応していくかを相談し、子宮内環境を守るために有効な方法を選択してもらいます。これは将来を見据えた、未来世代のための予防医学と思っております。
人間ドックと同じだと考えるとわかりやすいと思います。自分でお金を払ってリスクがどれくらい高いのかを知る。そして、自分で対策を選択する。個人的なレベルで子宮環境を自ら守る方法があるということを、今後、広めたいと考えているところです」
お話頂き、ありがとうございました。
化学物質に対して、胎盤は無力であるということ。
そして、今のおなかの中の赤ちゃんは例外なく化学物質に汚染されているという事実はとても衝撃的でした。
「個人レベルの曝露リスクを減らす努力が、最終的には社会的なレベルにまで引き上げることにつながると期待できる」と森先生はいいます。
胎盤が化学物質に対する関所にならないのであれば、母親、父親となる大人達の意識に化学物質に対する関所を設ける。それを、これから生まれてくる赤ちゃんたちを守るための第一歩としたいものです。
Interview
子ども環境問題 専門家インタビュー
アトピー性皮膚炎の原因と「ステロイドフリー」という治療法
木俣 肇 先生 守口敬任会病院アレルギー科部長
専門家インタビュー2
環境ホルモンと妊婦、胎児の関係
森 千里 先生 千葉大学大学院教授 医学博士
専門家インタビュー3
子どものからだと心がおかしい!身体が変わることで低下した“生きる力”
正木健雄 先生 日本体育大学名誉教授/子どものからだと心・連絡会議議長
専門家インタビュー5
小児白血病と電磁波の関係
齋藤友博 先生 国立成育医療センター研究所 成育疫学研究室 室長

子ども環境問題 インデックス
| babycom おすすめ記事 babycom Site |
子どもの発達の基礎知識とともに、最新の脳科学や発達科学の研究成果なども紹介し、環境や発達の視点から、健やかな脳に育てるために親が知っておきたいこと、親ができることを考える。

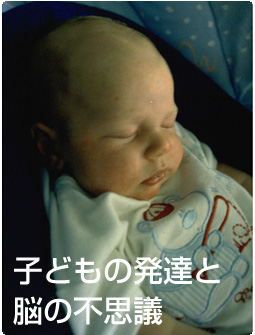 子どもの発達と脳の不思議
子どもの発達と脳の不思議