

ロハスな生活・新しい発想の提案-1
「地球」と「わたし」の双方にやさしい本当の快適性を探りながら、次世代につたえたい新しい価値観「ロハス」を実践する様々な工夫やアイデアを紹介します。
「地球とわたしの快適性-1」[対談]中村幸代 vs 上田昌文
協力/NPO法人市民科学研究室 2006年3月掲載


ロハスな生活・新しい発想の提案-1
「地球」と「わたし」の双方にやさしい本当の快適性を探りながら、次世代につたえたい新しい価値観「ロハス」を実践する様々な工夫やアイデアを紹介します。
「地球とわたしの快適性-1」[対談]中村幸代 vs 上田昌文
協力/NPO法人市民科学研究室 2006年3月掲載

「地球、自然、命ってすごい!という感動。そしてそれを守りたいという思いを音楽にこめて伝えたい」と語る音楽家の中村幸代さん。
「地球規模で起きている環境破壊の問題を、遠目で眺めるのではなく自分に一歩でもひきつけて考える。そのきっかけになるような情報を発信したい」という市民科学研究室・主宰の上田昌文さん。
活動の内容は大きく異なるけれど、見つめる先はどちらも同じであるそんなお二人に、地球環境について思うことを語り合って頂きました。
環境のこと、子育てのこと、自分たちにできること…楽しく続けられるロハスな生活のありかたが、そこから見えてきました。
![]() 中村幸代
中村幸代 ![]() 上田昌文
上田昌文 ![]() babycom
babycom
地球温暖化、森林の激減、環境汚染...
見えてきた、続けてゆけいない開発のゆくえ
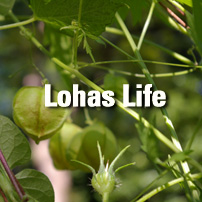
 地球やそこにつながる命のことを考えると、いつも感動する気持ちが持てる。それが私の音楽活動の原動力になっているわけですが、同時に地球が悲鳴をあげている事実も心を大きく占めています。「自然はすごい!」という気持ちと、その自然が失われてゆくことに対する「どうしよう?」という危機感を同時に持っているんです。
地球やそこにつながる命のことを考えると、いつも感動する気持ちが持てる。それが私の音楽活動の原動力になっているわけですが、同時に地球が悲鳴をあげている事実も心を大きく占めています。「自然はすごい!」という気持ちと、その自然が失われてゆくことに対する「どうしよう?」という危機感を同時に持っているんです。 森林の激減や温暖化など、地球規模で起こっている環境破壊のニュースをみていると漠然とした不安を感じるけど、なかなか自分の問題として肌で感じにくいということはありますよね。だから環境破壊は気になるけど自分でどうかしよう、という行動に結びつきにくい。
森林の激減や温暖化など、地球規模で起こっている環境破壊のニュースをみていると漠然とした不安を感じるけど、なかなか自分の問題として肌で感じにくいということはありますよね。だから環境破壊は気になるけど自分でどうかしよう、という行動に結びつきにくい。 そうなんです。わたしもロハスという考えに出会う前は、私個人がどうしようとこの状況は変わらないのかもしれない、というあきらめた気持ちを持っていたこともありました。エコロジーというストイックな考えは、私にとってはとても重く感じられるものだったこともあり…。
そうなんです。わたしもロハスという考えに出会う前は、私個人がどうしようとこの状況は変わらないのかもしれない、というあきらめた気持ちを持っていたこともありました。エコロジーというストイックな考えは、私にとってはとても重く感じられるものだったこともあり…。 なるほどなるほど、お任せください(笑)。
なるほどなるほど、お任せください(笑)。
 京都の会議では、アメリカが賛同しなかったということがとても印象に残りましたが…
京都の会議では、アメリカが賛同しなかったということがとても印象に残りましたが… アメリカの産業のシェアを大きく占めるのは石油や自動車など。それらの消費を抑えようという動きは、自分たちにとって非常にマイナスだと考えているからですね。でもね、そうした考えを続けているとおかしなことが起こってくることになると思いますよ。
アメリカの産業のシェアを大きく占めるのは石油や自動車など。それらの消費を抑えようという動きは、自分たちにとって非常にマイナスだと考えているからですね。でもね、そうした考えを続けているとおかしなことが起こってくることになると思いますよ。
「自分だけなら大丈夫」ですまされない
そのワケは....

 規模が大きいだけに、その影響は世界に巡ってくるのでしょうね。アメリカの問題は、世界の問題につながるのではないですか?
規模が大きいだけに、その影響は世界に巡ってくるのでしょうね。アメリカの問題は、世界の問題につながるのではないですか?
 そのとおりです。たとえば、遺伝子組み換え食品のことでもそう。日本で売られているサラダ油の大半はアメリカ産の大豆を原料にしています。そしてまた、油を絞ったあとの大豆の搾りカスは、日本国内の飼料として畜産にも使われている。
そのとおりです。たとえば、遺伝子組み換え食品のことでもそう。日本で売られているサラダ油の大半はアメリカ産の大豆を原料にしています。そしてまた、油を絞ったあとの大豆の搾りカスは、日本国内の飼料として畜産にも使われている。 それは見えない問題ですね!
それは見えない問題ですね!
 そこが環境問題のコワイところ。経済のグローバル化がすすめばすすむほど、私たちの手にしているモノの由来がつかみにくくなる。そのモノが出来上がり自分のところに届くまでに、どれだけのエネルギーや水などが使われているかは、もう直感ではとらえられなくなっている。自分の問題が世界につながっているのに、それが見えないのです。
そこが環境問題のコワイところ。経済のグローバル化がすすめばすすむほど、私たちの手にしているモノの由来がつかみにくくなる。そのモノが出来上がり自分のところに届くまでに、どれだけのエネルギーや水などが使われているかは、もう直感ではとらえられなくなっている。自分の問題が世界につながっているのに、それが見えないのです。
環境への配慮を楽しむ、という新しいセンスが「Lohas」
そのワケは....
 先ほど、個人レベルの対策は環境問題の解決に結びつかない、という話がありましたよね。でもそれは大きな誤解。私は「個人の選択が社会へ跳ね返る」と考えています。
先ほど、個人レベルの対策は環境問題の解決に結びつかない、という話がありましたよね。でもそれは大きな誤解。私は「個人の選択が社会へ跳ね返る」と考えています。
たとえば遺伝子組み換え大豆を使ったサラダ油を選ばない。国内産の無農薬の大豆を使っている油を選べばいい。モノによっては表示が必ずしも正確に現実を反映していないこともありますが、少なくとも環境にも負荷が小さくて人体にもより安全な品を意識的に選ぶことはできるでしょう。それもひとつのエコロジー運動でしょう。
今、環境をよくしようという技術もどんどん生まれています。環境配慮型の企業もたくさんある。そうした企業に賛同する。そこへお金を落とす。するとその企業はどんどん元気になりますよね。すると社会全体が環境配慮型へ動きます。
 少しでも環境にやさしいほうを選ぶ、というのは中村さんも実践しているロハス的な発想ですね。
少しでも環境にやさしいほうを選ぶ、というのは中村さんも実践しているロハス的な発想ですね。
 環境にも自分にもやさしく、というものですよね。ストイックな印象があって犬猿されがちな「エコロジー」も、もともとはギリシャ語で「オイコスoikos=家、生活の場」という意味なんですよ。
環境にも自分にもやさしく、というものですよね。ストイックな印象があって犬猿されがちな「エコロジー」も、もともとはギリシャ語で「オイコスoikos=家、生活の場」という意味なんですよ。
19世紀半ばくらいから、生物と環境の相互作用や生物集団どうしの相互作用を研究する学問(「エコロジー=生態学」)が出来上がってきたのですが、その学問ジャンルを指す「エコロジー」という言葉が、次第に、人間が環境を守り自然との共存をはかる文化や思想や運動など全般的な営みに対して用いられるようになったのです。
 もともとは家計や家庭のエネルギーを考えるものでもあったんですね!
もともとは家計や家庭のエネルギーを考えるものでもあったんですね!
今まではエネルギーの問題を考えて世界に目を転じると、水の汚染、空気の汚染…問題が大きすぎて暗い気持ちになってしまいがちだったのですが…
 いきなり大きな問題を自分の生きている間に解決しなくちゃいけない、と考えると辛くなると思うんです。かえってもういいや、とあきらめた気持ちにもなってしまうかもしれない。だから、生活のなかでどうやったら面白く賢く環境に配慮してゆけるかを考えるといいと思うんです。
いきなり大きな問題を自分の生きている間に解決しなくちゃいけない、と考えると辛くなると思うんです。かえってもういいや、とあきらめた気持ちにもなってしまうかもしれない。だから、生活のなかでどうやったら面白く賢く環境に配慮してゆけるかを考えるといいと思うんです。
それをうまく表した言葉が「ロハス」なのかもしれません。
 |
| babycom おすすめ記事 babycom Site |
毎日の食生活を見直すことで、地球環境に何らかの働きかけはできないものか!
子どもたちの心や身体そして地球環境にやさしい食生活について考える。

|
お母さんと赤ちゃんの栄養学 授乳しているお母さんの健康のための栄養、食べるとよい食材とその量について。 |

|
わが子のペースではじめる 離乳食はいつから? 何を食べさせたらいいの?が子のペースに合った離乳食のコツを伝授。 |
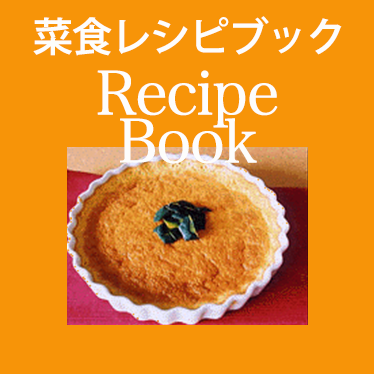
|
菜食レシピ 旬の野菜を使った一味違う「イタリアン和風」のからだにやさしいレシピ。 |