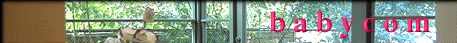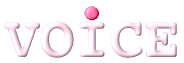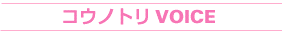培養士さんに無駄な卵と言われました 培養士さんに無駄な卵と言われました |
さくら -- 2005/12/12 .. | ||
|
今まで良好胚、胚盤胞などを移植しても着床しなかったので、今回は2日目のETを希望しました。 2日目でグレード3の5分割と4分割でした。今週期は採卵時に内膜が7?を越えていたので、移植できると考えていました。 私は、クロミッドの自然周期のため、移植時の内膜はいつも7?程度だったからです。それでも、胚の質と内膜の形が重要と言うことで移植してきましたが、着床しませんでした。 今週期は内膜の状態がいいので、試してみたかったのですが、グレードがあまりよくないため移植が出来ませんでした。 前回は、3日目でグレード3の7分割で、内膜も移植時に8?弱だったのに移植しました。 今回と前回の違いを培養士さんに伺うと、グレード3でもいろいろな段階があると説明を受けました。素人の私にはグレード3と聞けば、前回と同様な感じなのかと考えてしまいます。 それに、医師からはグレードはあまり気にしないように、とも言われることもあります。 そのため納得が行かなかった私に、その培養士さんは「無駄な卵を戻してもしょうがない」と言ったのです。 結局今回は、胚盤胞にならずグレード3のまま8分割と7分割で成長が止まってしまたわけですが、早く子宮に戻してあげたかったと言うと、培養液と子宮の中の環境は変わらないと言いきられました。 その培養士さんから見れば、受精や分割をしない胚は、廃棄物の扱いにしかならないのは分かっているけど、培養士さんの技術に頼って顕微受精をしている私の立場はどうなるのでしょうか。 そのように考えている培養士さんが居ることに、ショックを受けました。落ち込んでしまって、これからどうしようか、とても悩んでいます。 |
|||
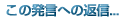 |
|||
 hinahinaさん 杏仁豆腐 hinahinaさん 杏仁豆腐 |
|||
 拝見させて頂きました。 さくら 拝見させて頂きました。 さくら |
|||
 杏仁豆腐 さま hinahina 杏仁豆腐 さま hinahina |
|||
 hinahinaさんへ 杏仁豆腐 hinahinaさんへ 杏仁豆腐 |
|||
 培養士とは hinahina 培養士とは hinahina |
|||
 ありがとうございます。 さくら ありがとうございます。 さくら |
|||
 医師からのインフォームドコンセントは? hinahina 医師からのインフォームドコンセントは? hinahina |
|||
>>>
 hinahinaさん hinahinaさん |
杏仁豆腐
-- 2005/12/12.. | ||
|
hinahinaさんありがとうございました。 hinahainaさんの文章を何度か読み直し、ご意見見解同意できること多々です。 次回病院に行ったら、いろんな質問をしてきたいと思います。 <医師からは、ICSIによるメリットデメリット。 体外受精によるメリットデメリットについてそれぞれ説明がありましたでしょうか? 本当に少し考えたらわかることですよね。説明はありませんし、聞いてもいませんでした。 麻痺してきているのかもしれません。 今転院してとてもよい病院なので前よりいろんなことがわかってきて、 なのでそれ以上については質問さえしていません。 IVF(ICSI)をする前はで必ず授精をするものだと思っていたのです。 ところが、いろんな書き込みを見ていると授精さえしないということが わかり、本当に生命誕生には難関がたくさんあるのだということに 治療を進めて行くにしたがって実感いたします。 しかし、授精しなければ次には到底進めません、いろいろと先生と相談して 治療を決めていきたいと思います。 ありがとうございました。 短文にて申し訳ありません | |||
>>>
 拝見させて頂きました。 拝見させて頂きました。 |
さくら
-- 2005/12/09.. | ||
|
hinahina 様。 培養士の解説をありがとうございました。【JRD2004年4月号(vol.50,No.2)掲載】を拝見しました。 おかげ様で、培養士についての詳しい内容を把握することが出来ました。新しい分野の資格だと思っていましたが、専門機関がまだ確立されていない上に、経験年数の浅い培養士が大半を占めていることもわかりました。 hinahina様は、医療についてかなりご精通されていると、お見受けいたしました。hinahina様がおっしゃられたように、培養液は既製品ですし、病院を替えてもあまり差はないのかも知れません。そのため、今はどこの病院に転院するか検討中です。 今回、見ず知らずの私の発言に対して、こんなにもご親切なご発言を承りまして、感謝の気持ちで一杯です。とても、救われたような気が致しました。本当に、ありがとうござました。 | |||
>>>
 杏仁豆腐 さま 杏仁豆腐 さま |
hinahina
-- 2005/12/09.. | ||
|
杏仁豆腐 さま 顕微授精(ほとんどの場合はICSIによると思います。) これから挑戦できる回数というファクターがありますので、結論から言うとなんともいえないです。 医師からは、ICSIによるメリットデメリット。 体外受精によるメリットデメリットについてそれぞれ説明がありましたでしょうか? 人間において大規模な実験は行なえませんし、母親父親双方の身体的な条件も千差万別ですので、明確なことはいえませんが、動物実験では、精子・卵子がほぼ同じ条件での標準的体外受精胚とICSI受精胚との比較では、ICSI胚のほうがわずかながら、その後の発生率が悪いとの報告が複数あります。実験では、かなり理想的な条件で行なわれていますので、これをそのまま人間に当てはめることには注意が必要です。 科学的判断をすれば、卵に穴を開けるICSIより先に標準的な体外受精を行い、その経験の上で、次のステップを考えるのが当然のことと思います。しかし、不妊治療では無限回数、繰り返しトライできないわけですから、「高度な政治的判断?」を要求されるわけです。これまでの治療暦などを総合的に考慮したうえで、患者ののぞむ治療を選択するのがよいのではないかと思います。 標準的な体外受精では、シャーレの中でおきることは患者の精子・卵子に任せて、うまく受精することを祈るだけです。クリニックもしくは培養士に求められることは、受精に適切な環境を維持することぐらいのものです。受精するしないは、「運」なわけです。決して安くない治療費と、それ以上に精神的にも身体的にも負担のかかる不妊治療において、その入り口である受精の段階で、この「運」まかせであることを、患者が受容できるかどうか迷うところだと思います。 それに対して、ICSIは少なくとも精子を一つ卵子に注入するという作業を顕微鏡の下で行いますから、「何か難しい作業」を行なったという、「満足感」のようなものが得られます。加えて精子側の運動性かかわる未受精の可能性を減らすことはできます。またクリニックも客商売でありますから、少なくとも患者が「最新で優れている」と思っている手法を、積極的に取り入れることは、宣伝効果もあります。加えて、不幸にして期待にこたえられなかったときに「ここまでしたのだから」という言い訳ができます。(これは、患者本人にとってもクリニックにとってもですが。) いずれにしても、このあたりの説明を培養士まかせにするというのは、問題だと思います。一般的なクリニックにおける給与体系からして、「マニュアルにしたがった作業が出来る。」以上のことは、培養士に期待していないように思います。 患者は弱い立場と思わないでください、あなた様は顧客なわけです。そしてあなたには、自分の治療方針について説明を求める権利があります。どうしたって、確率をある程度高めることはできても、最後は「運」なのですから、医学的な明らかな不利がない場合には、結果のいかんを問わず、自分が納得の出来る選択をするしかありません。 >運動率がよければ、顕微と体外はほとんど変わりない可能性で授精できるのでしょうか? 卵子の状態にも左右されますから、なんとも言えません。また精子についても一般的な運動率だけで受精率を予測することには限界があります。標準的な体外受精を何度か行なった経験があり、そのときの受精率が悪い場合には、顕微による受精率の向上を期待します。期待するとは、期待通りに受精率が向上する場合もあれば、不幸にしてそうならないケースもあるからです。 逆に、体外受精において受精率に問題がない場合に、あえて顕微を行なう必要性を多くの場合には見出せません。男性側の何らかの問題(疾患)から、特定の性質をもつ精子だけを利用したい。または排除したいなど特別な理由があるときには話は別です。 | |||
>>>
 hinahinaさんへ hinahinaさんへ |
杏仁豆腐
-- 2005/12/08.. | ||
|
こんばんは、今回別に質問ださせていただいたのですが、今hinahinaさんの内容を見て、聞きたいなと思い書き込みします。 >精子の状態が良好でであれれば、顕微と体外受精には発生率に大きな差はありません。逆に、卵に直接穿孔をする顕微授精のほうが、発生率がわずかに劣るというのがが一般的です。 今回精子の運動率よかったので体外ができると思っていたのですが、 培養士さんから卵が2個なのと年齢で(40歳)顕微を勧めます。といわれ、結局顕微になりました。 こちらからすれば一ヶ月に一回の採卵で大切なのでわらにもすがる思いで いますので、顕微でといわれればそのようにしてしまうわけでして・・・・ 今回読ませていただいてちょっと考えてしまいました。 前回精子の運動率が悪く顕微になってしまい、今回主人はサプリのんだり 食事の気をつけたりでかなりの努力したのです。 それで、精子の状態がよかったのですごくうれしく思ってたら 顕微を勧められたので・・・・ 結果はまだ出ていないのですが、なんとなくすっきりしないままでした 運動率がよければ、顕微と体外はほとんど変わりない可能性で授精できるのでしょうか? 教えてください。 また先生に聞いてみるべきでしょうか? | |||
>>>
 培養士とは 培養士とは |
hinahina
-- 2005/12/07.. | ||
|
培養士とは、どういう資格かということについて解説がありますので、紹介いたしておきます。 【JRD2004年4月号(vol.50, No.2)掲載】で検索してください。 正確には、生殖補助医療胚培養士資格制度といいまして、 《補助》することができる人であって、医療行為そのものを行なえる資格ではありません。ですから、どこの病院にしろ、説明を培養士まかせにするということは、許されるものではありません。クリニックもしくは医師の質にたいして「馬脚を現した」という事案であると思います。 >クリニックが培養の過程を分けているようです。 クリーンな培養室を維持しなければなりませんから、別室に準備します。 受精卵の取り扱いは、技術的に特殊なものではなく、マニュアルにしたがった手先の作業です。特殊な薬剤や電気パルスを用いるような”逆に挑戦的な方法”は、医師の判断と、それこそ十分なインフォームドコンセントがなければ出来るものではありません。 培養士の仕事は、病気の治療の場面で、看護士・作用療法士・レントゲン技師・臨床検査技師などがいるのと同じで、分業なわけです。繰り返しになりますが、健康診断で血液検査やレントゲン撮影を行なったとき、その結果について、レントゲンを撮影する技師の方や、血液検査をする技師の方が、結果について、あなたに説明するでしょうか? 培養士もそれと同じです。 クリニックを変えることを検討されておられるようですが、培養方法もちいる薬品などについては、多くの場合大差はありません。精神的なケアのよいクリニックにめぐり合えることをお祈りしています。 >体外受精は数回しか行っていませんが、その数回とも経過は良好でした。体外受精でも可能ですが、顕微受精での治療がほとんどです。 私には、この方針が理解できません。精子の状態が良好でであれれば、顕微と体外受精には発生率に大きな差はありません。逆に、卵に直接穿孔をする顕微授精のほうが、発生率がわずかに劣るというのが一般的です。顕微授精は一般に、男性不妊に対する成績向上を目的としたものです。卵・精子ともに何らかの医学的理由で、顕微のほうがよい場合もあります。ですから担当医とよく相談することが大切です、精子の状態がよく、卵子の状態にも問題がなければ、顕微授精のほうが体外受精より優れているということはありません。「最新」=「もっとも優秀」という図式ではありません。 | |||
>>>
 ありがとうございます。 ありがとうございます。 |
さくら
-- 2005/12/05.. | ||
|
hinahina 様。 倫理的でしかも明晰なお応えを頂きまして、誠にありがとうございました。私の拙い文章からすべてを汲み取って下さったような気が致しました。 私は複数の病院に通いましたが、現在通っているクリニックでは移植が出来る出来なに関わらず、医師からの胚の説明はほとんど受けたことがありません。 それがそこのクリニックの方針なのだと思います。 でも、今まで通っていた病院では、すべて医師から胚の説明を受けました。ほとんどの病院では、高齢の為に顕微受精となり、現在のクリニックでもそうなりました。 体外受精は数回しか行っていませんが、その数回とも経過は良好でした。体外受精でも可能ですが、顕微受精での治療がほとんどです。 顕微受精でも高度な技術がある培養士の方なら、安心して任せられる気がするのですが、毎回どうのような方が行うかどうかわかりません。 ある大学病院で治療を受けていた時に、研修医のような方が、先ほど顕微受精を行ってきたと雑談していました。 確かに、医師ならすべての工程を出来るわけです。ただ、ほとんどのクリニックが培養の過程を分けているようです。 現在通っているクリニックは個人の医院ではないので、医師によっては診方に多少の違いがあるのかもしれません。 今のクリニックからは転院をすることを考えていますが、不妊治療の場合、メンタル部分の配慮を求めるのはかなり厳しいようです。 大変ご丁寧な内容のご返信を頂きまして、とても感謝しています。本当に、ありがとうございました。 | |||
>>>
 医師からのインフォームドコンセントは? 医師からのインフォームドコンセントは? |
hinahina
-- 2005/12/02.. | ||
|
さくらさま 培養士からの説明だけですか? 医師からのインフォームドコンセントはありませんでしたか? 受精卵を子宮内に戻すかどうかについては、科学的根拠に基づいた何らかのマニュアルに従って、判断しているものと推察します。しかし、培養士からの説明だけで、医師からの説明が何も無いとは考えられません。もし、医師からのインフォームドコンセントがなかったとするならば、私は、別の病院に行くことも選択肢に入れるべきだと思います。 不妊治療は、精神的にもかなり負担が大きいものですから、冷静になれない場合もあり、意志の疎通がうまくいかないこともあるかと思います。しかし、もう一度、冷静に判断して、医師からの説明が無いとなると、その病院はあまり感心できません。 「今回の胚の状態を、「○×△」に基づいて精査した結果、着床して発生する可能性は、「○△」以下と考えられる。つまり、この胚を戻しても、妊娠する可能性は極めて低いのに対して、移植は少なからず母体(さくら様)に負担をかけることになり、医学的にメリットとデメリットを考慮した場合、デメリットのほうが、はるかに大きいので、今回は行わないほうが良いと判断する。」最低限、この程度の説明は必須であると考えます。また、これは、医師が同席すべき内容です。 培養士ですが、技術的なレベルは、最低限保証されていても、専門的知識レベルは、ずいぶんマチマチです。ですから患者に対して、培養士がインフォームドコンセントを適性に行えるかどうかには疑問があります(かなり個人差が大きいように思います)。 人によっては、ウシやマウス(実験動物)を主戦場(教育や研究の中心)としてやってきた人も、培養士の中にいます。もちろん、技術水準に疑問をはさむわけではありませんが、少なくとも「人間の患者」へのメンタル的な接し方について、未熟な者がいる可能性を私は否定しません。培養士は、最終的な判断を下せませんから、説明は医師が同席する場でされるべきと思います。技術的水準からすれば、臨床検査技師の系よりも、マウスの胚を毎日、数百個単位で扱ってきた連中(理学部や農学部卒)のほうが、イケテイル場合もありますから、培養士になれる人を臨床検査技師などに限るような、規制が入ることには賛成できませんが、最低限、生命倫理や患者とのかかわりについては、みっちり教育した上で現場に出すべきだと考えます。 | |||